旅人とわんこの日々
世田谷編 2004年Page6
ワンコのいる日常と旅についてつづった写真ブログです。
6、箱根ツーリング2004(2004年4月30日)
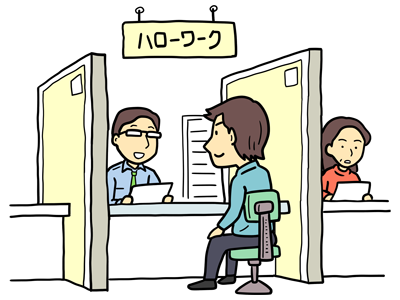
(*イラスト:poosanさん 【イラストAC】)
メキシコ、南米の旅行から無事に帰国し、現像に出した写真の整理や、ペルーで遭った盗難の保険申請などの後始末が落ち着くと、ハローワークに行き、ボチボチと就職活動を始めた。
が、分かってはいたが、そうそう簡単に仕事が決まるものではない。まあ気長にやっていくしかないだろう。そんな折、友人が箱根にツーリングに行かないかと誘ってくれた。
前回のユーラシア大陸横断旅では、出発前にバイクを売ってしまったので、日本に帰国してもバイクがなく、不便をした。今回は旅程も短かったので、売らずにバイクカバーをかけ、自宅の車庫に厳重に保管しておいた。
おかげで帰国してもすぐにバイクに乗ることができた。しかも3か月ぶりにエンジンをかけたというのに、一発でエンジンがかかったのにはちょっと感動した。

最近のバイクは凄いな・・・。ちょっと専門的になるが、一昔前はキャブレターという機械的にガソリン噴出する装置が当たり前で、気温の低い季節にはチョークを引いてエンジンをかけたりと、色々とバイクと対話しながら乗っていた。
それが今ではインジェクションというコンピューター制御に変わったので、気温などの環境に左右されることがないし、基本的にメンテナンスも必要ない。おまけに今回のようにちょっと乗らなくても、バッテリーが上がっていない限りエンジンが一発でかかってしまったりする。インジェクションって凄いな・・・と、改めて実感したのだった。

箱根ツーリングの日は快晴。しかもこんなに天気がいいのも珍しい・・・。というより、今まで何十回と訪れたが、歴代で最高のコンディションではないだろうか。
空気がもの凄く澄んでいて、富士山の見え方が半端ない。ここまでくっきり富士山が見えると、天下の絶景といった感じで肌が立つほど美しく感じる。

こういう日に富士山を眺めながらバイクで走ると本当に気持ちがいい。心の中のもやもやも吹き飛んでくれる。
もちろんそれは一時的な誤解で、帰宅すると、再び就職のことで頭を悩ませなければいけないのだが・・・。でもバイクに乗っているときだけでも、忘れていたいものである。

友人は私と同じ学年。なので、あと数年で30才、いわゆる三十路を迎える。その前に色々と挑戦をするんだと、ツーリングの最中に熱く語りだした。
なんでも今年はサーキトに行き、サーキットでの走行を頑張る予定だとか。後は一人で遠くにツーリングも行きたいとのこと。何やら私の旅行に感化され、積極的になっているようだ。
後輩の方は今年はどうかわかりませんが、結婚を・・・とそれぞれ夢があっていい。しかも、富士山を背景に夢を語ると、その夢がすぐに実現しそうな雰囲気がする。

これは俺も便乗しておこう。就職活動頑張るぞ。いや、早く、就職が決まってくれ・・・と、一人だけ何か現実的で悲痛な願いを富士山に叫んでいたのだった。
7、旅人の就職活動(2004年5月~6月)

家庭の事情、仕事の環境、その他もろもろあり、30才を間近にして仕事をやめ、メキシコを中心に3か月ほど中南米地域をふらふらと、いや、精力的に旅をしてきた。
旅をしているときは楽しく、人生が充実しているように思えるのだが、問題はその楽しい時間が終わった後になる。
帰国後には新たな仕事場で・・・といった確約もなく旅に出たので、当然というか、日本に戻ると無職の風来坊。午前0時を刻んだ後のシンデレラといった状態だった。
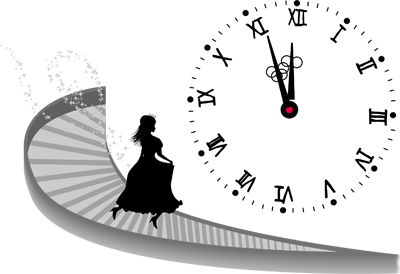
(*イラスト:ニッキーさん 【イラストAC】)
旅のように行き当たりばったりな生き方をしていてはいかんな・・・と思うのだが、こういった性格をしているのでしょうがない。
でもまあ、旅では行き当たりばったりでも、臆することなく進んでいけばなんとかなるもの。時にはトラブルに巻き込まれることもあるが、親切な人や通りすがりの人に助けられて、最終的には何とかなっている。
旅は人生の縮図。人生だってきっと同じこと。日本の常識ではありえないような窮地を幾度となく乗り越えてきた私には、普通の人とは違った純度の高い人生経験が蓄積されているので、きっと何とかなるはず。
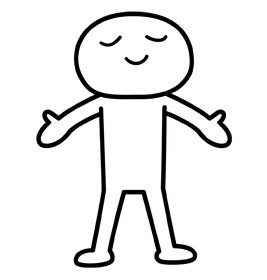
(*イラスト:ちょこぴよさん 【イラストAC】)
だいたい人生なんてなるようにしかならないのだから、あまり先のことばかり考えたり、難しく考えてもしょうがない。それが人生を楽しむコツというものではないか。・・・などと強がりながら、ぼちぼちと就職活動を始めた。

何年か前にはユーラシア大陸を横断したし、学生時代には飛行機で地球一周もしている。今回はメキシコや南米を回ってきた。
哲学者のアウグスティヌスの言葉に 「世界は一冊の本にして、旅せざる人々は本を一頁しか読まざるなり」とある。偉大な哲学者の言葉通りなら、世界を旅してきた私は見聞が広く、分厚い辞典に負けないほどの知識人であり、地球規模で物事を考えられる視野の広い人間となる。

(*イラスト:実鈴さん 【イラストAC】)
うすうす感づいていたが、私はかなりの大物で、誰もが欲するような人材ってやつではないだろうか。そうだ。そうに違いない。
自信満々にハローワークで紹介された会社の面接を受けるものの、学生の就職活動ならいざ知らず、いい歳した人間が旅の何たるや、旅で得られる経験の素晴らしさを一生懸命話しても、面接官にいい印象を与えるはずがない。
そもそもとして、ハローワークに求人を出す会社が世界を知るような大物の人材を求めていない。浮ついた感じで世界を語る人間よりも、堅気に仕事を積み重ねてきて、それなりに実務スキルを持った人間を欲している。そう、訪れた国の数よりも、持っている資格の数の方が重要なのだ。
履歴書を送っても面接にこぎつけるのも大変であるが、面接を受けてもなかなかいい反応をしてもらえなかった。

(*イラスト:まぽさん 【イラストAC】)
なかなかいい仕事が見つからないものだ・・・。日本の村社会的な考え方はグローバルな私とは相性が悪い。日本は俺には狭すぎるんだ・・・。と、なるべく自己肯定的に考えるようにしていても、就職が決まらないという現実は変わらない。「郷に入っては郷に従え」とあるように自分が変わるしかない。
結局のところ、あちこち旅をして見聞を広めても、就職にはほぼ役に立たない。そんな当たり前のことにようやく気が付いた・・・と書きたいところだが、それはもうとっくに大学時代の就職活動で学んでいた。

(*イラスト:ジュンズ10さん 【イラストAC】)
「若いうちに旅に出ろ」という言葉をよく聞くと思う。若い柔軟な思考を持っているうちに違った文化や考え方に触れることは、その後の生き方、考え方にいい影響を与えるといった趣旨であるが、それ以上に自分の知らない土地を、自分の目で見て、自分の頭で判断し、自分の力で行動することがいい人生経験となる。それは多くの人が認めることである。
なので、多くの土地を旅してきた見聞の広さ、海外を一人で旅する行動力や積極性をアピールすれば、面接官にいい印象を与えそうなものであるが、それは世間話とか、コンパや趣味のサークル、町内会の会合などといった場所での話で、就職の面接においてはあまり当てはまらない。
何か飛びぬけた実績とか、世間が認めるような成果をあげていないと、ただ旅が好きな人間となってしまうだけ。そもそも旅の道中のことは本人しか知らない。いくらでも話を盛ることができてしまう。

(*イラスト:hozuさん 【イラストAC】)
大学在籍時の就職活動でも、海外一人旅はサークル活動と同じ扱いとなり、しっかりとした学校の成績や国際交流などといった目に見える実績の方が大事になる。
社会人ともなるとさらに厳しくなり、ただ漠然と海外の文化に明るいとか、視野が広いというだけでは、「あっ、そうですか」と門前払いされる。
海外を旅した経験をどう仕事に生かせるかといった視点が重要になり、少なくとも英語がペラペラにしゃべれるとか、英検やTOEICなどの資格を持っていないと、その話に真実性がなくなるので、なかなか苦しい。
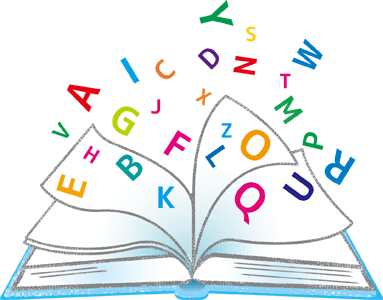
(*イラスト:くらうど職人さん 【イラストAC】)
もちろん旅してきたことが無駄とか、全く役に立たないわけではない。明らかに普通の人とは違う経験をしてきたので、いわゆる積極性があり、強烈な個性がある人間となり、同じレベルで迷った場合、旅好きなあいつにしておこう。知識豊富で話が面白そうだし・・・。ってなことになりやすかったりする。
また、職種によっては外国人の労働者が多いとか、客に外国人が多い場合、外国人に慣れているからと重宝されることもあったりする。
とはいえ、それは面接官や会社の社風に旅人という自由な個性がマッチしていた時の話になる。そうでないと、旅好きというだけで、仕事に身が入らなさそう・・・などと、ひどく減点されかねないので、諸刃の剣というのが実際だろう。ほんと、旅の評価、いわゆる旅人の通信簿というのは難しい。
世田谷編 2004年Page6 2004年Page7につづく
