旅人とわんこの日々
世田谷編 2004年Page11
ワンコのいる日常と旅についてつづった写真ブログです。
13、白黒写真(2004年6月下旬)

せっかくチワワの故郷であるメキシコに行ってきたので、チワワのポーちゃんに土産話をしてやりたいと思っていたのだが、メキシコ旅行後は、就職活動や屋久島ツーリングとバタバタとした生活をしていて、なかなか会う機会がなかった。
屋久島ツーリングから帰った3日後、妹が犬を連れてやって来た。久しぶりの再会となる。半年ぶりになるだろうか。
もう生後1年以上経ったが、相変わらずちっこいまま。もっと大きくなってもいいのでは・・・などと、余計な心配をしてしまったりするが、体毛の方はしっかりと伸びたようで、また一段と可愛らしくなっていた。

カメラの中には屋久島ツーリングの時に入れていた白黒のフィルムが入ったまま。さっさと現像に出してしまうためにも、今日は白黒フィルムで撮影してみた。
どんな感じで映っているのだろう。白黒だと普通のネガよりも現像のときの楽しみが大きい。その分、料金も少し高くつくけど・・・。


ビアデッドコリーのチャーミーの場合は、元々毛色が白黒なので、白黒の写真でもあまり変わった感じはしない。
でも、陰影とか、カラーのない静寂な感じとか、白黒にしてみるといつもと違った味わい深さを感じる・・・こともある。まあそのへんは腕次第ってことになるのかな。
14、初出社(2004年7月1日)

(*イラスト:モーモーファクトリーさん 【イラストAC】)
今日は新しい会社の入社日。30近くにして、また新入社員になった。もう慣れっこ、などと言うほど転職はしていないが、アルバイトを含め多くの職場を経験してきたので、普通の人よりは幾分こういう状況には慣れている。
月並みだが、何事も最初が肝心。初日から嫌な奴と思われると、無駄に苦労することになる。最初の一歩がうまくいけば、次の一歩も進めやすくなるし、その後も修正が楽というもの。
ということで、なるべく印象よく、そして初々しくといった感じで、緊張と期待を胸に初出勤した。
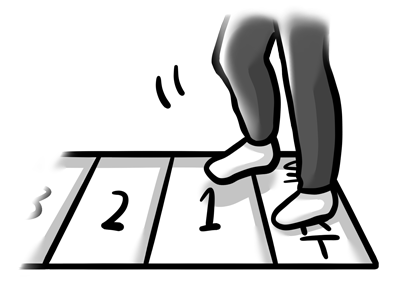
(*イラスト:ハコさん 【イラストAC】)
新しい職場に順応することは、旅で新しい土地に順応するのに似ている。人々の様子をしっかりと観察し、空気を読みながらコミュニケーションをとっていく。誰に話しかければ効率よく輪に入っていけるのか。踏んではいけない地雷は何かをしっかりと見極める必要がある。
と、もっともらしく旅に絡めて書いてみたが、学校生活でも、クラブ活動でも、職場でも、転居先の町内会でも同じこと。旅に関係なく、人間関係の基本的な理になる。
むしろ旅の場合だと、一時的な関係にしかならないので、あまり参考にならない。いや、それどころか、日本の社会環境で旅をしている時のようにふるまうと、確実に人間関係がうまくいかない。そう、旅の場合は少々図々しい態度で振舞っていても、相手の方が物珍しがって合わせてくれるからだ。

(*イラスト:カフェラテさん 【イラストAC】)
職場においても、旅と同じ行動をすると、初日は面白いやつとなるかもしれないが、すぐに「図々しいやつ」「態度がなっていない」「常識がない」「輪を乱す」と、腫れもの扱いとなってしまう。
なので、最初のうちはなるべく角が立たないように過ごし、自分をその場に馴染ませるようにしている。
郷に入っては郷に従え。ある意味名言で、日本の村社会においてはとても重要な掟になる。とはいえ、多くの海外生活を経験すると、日本ってなんか暮らしにくいな・・・。考えが狭いな・・・。薄情で思いやりがないな・・・と思う場面も多い。
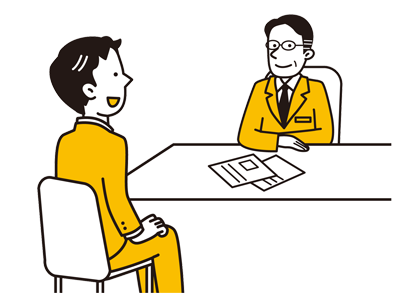
(*イラスト:うさぎやさん 【イラストAC】)
さて、初出社。チェーン店の実店舗に配属された。私を面接した面接官は、やる気がみなぎっている印象が強かった。職場もそういったやる気に満ちていて、仕事にやりがいがあるのでは・・・などと、勝手に想像して初出社したのだが、なんかちょっと雰囲気が暗い・・・。というか、働いている人に覇気があまり感じられない・・・。
たまたまこの店舗だけだったらいいのだが、他の店舗に移動してもこんな状態だと、しんどいな・・・。
この環境で個性の強い私が受け入れられるのだろうか。自由奔放に生きている私が長くやっていけるだろうか。1カ月もしないうちに角が立って、居づらくなってしまうのではないだろうか。

(*イラスト:のらつぎさん 【イラストAC】)
給料も安いし、休みも少ないし、また旅に出たり、転職するような人生を歩んでしまうのではないだろうか。今回の職場も、旅で訪れた村と同じで、一時的な滞在となってしまうのだろうか。出社初日から失敗したかな・・・と、自分の将来に不安を感じてしまうのだった。
15、異国情緒(2004年9月)
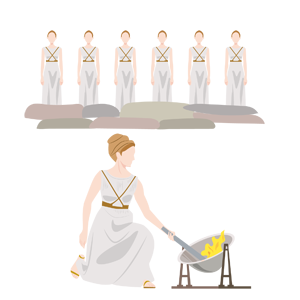
(*イラスト:トムセン少佐さん 【イラストAC】)
気がつけば九月。異常に暑く、異常に台風の多かった夏が終わるとともに、オリンピック発祥の地で行われることで注目を集めたアテネオリンピックも、無事に閉会した。
今回のオリンピックでは、男子体操に女子マラソン、競泳、柔道やレスリングなどで、合計16個もの金メダルを日本選手団が獲得した。
テレビでは連日その話題が取り上げられ、人と話しても自然とオリンピックの話題になることが多く、とても盛り上がった大会になったように思う。

(*イラスト:ソーガさん 【イラストAC】)
オリンピックの開催国ギリシャとの時差は6時間。現地の午後6時は、日本時間では午前0時となる。盛り上がる種目の決勝は、現地のゴールデンタイムに行われるものが多く、ライブ中継を見ようと思うなら深夜の観戦になってしまう。
これが日中とか、真夜中とかなら諦めもつくが、ちょっと我慢して起きていれば見れてしまうというのが厄介で、ここのところ睡眠が不規則になりがちだった。
オリンピックが終わったことで、睡眠不足気味の日々から解放され、そして夏が終わったので、朝晩には通学の学生の姿を多く見かけるようになり、色んな意味でありふれた日常が戻ってきた感じがする。
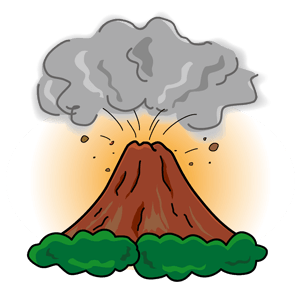
(*イラスト:iccoさん 【イラストAC】)
日常が戻ってきたとはいえ、9月に入ってからは浅間山が噴火したり、三重の方で大きな地震が起きたりと、今年は災害が多いのが気になる。
海外に目を向けると、3月にはスペインのマドリードで、同時多発列車爆破テロ事件が起きたり、日本人ボランティアがイラクで人質になったりと、なかなかきな臭い。オリンピックの話題に隠れているが、今年は暗いニュースが多いような気がする。

暗い話はさておき、今回はオリンピックロスと、ちょっと海外旅行を懐かしんで、異国情緒を感じるワンコ写真を紹介することにしよう。

(*イラスト:ヨッシーさん 【イラストAC】)
イスラム教徒などの女性が宗教的な理由で頭に被るベールのことをヒジャブという。
こういった習慣はイスラム教だけではなかったり、国や地域によってその重要度や意味合いが異なり、全身真っ黒で顔もすっぽり覆われていたり、目の部分だけ開いていたり、逆に華やかな感じでお洒落の手段になっていることもある。などと、海外見聞が多い旅人らしく、ちょっと知識をひけらかしてみたりする。

我が家のワンコも女の子なので、これで立派なヒジャブ女子。毛布を頭に巻いただけなのだが、けっこう似合っているように思う。

我が家のチャーミーは垂直に座ることが得意だ。下が柔らかい場所ならそこそこ長い時間この体勢でいられる。
腕を交差させるような仕草はまるでコサックダンスをしているようにみえる。そのまま踊りだしたら楽しいのだが、さすがにそこまではできない。

(*イラスト:えふ子さん 【イラストAC】)
そしてこの応用版というか、「おんぶ」と言うと、人間の背中におんぶすることもできる。おんぶ犬。滅多にいないので、実は近所ではちょっと評判になっていたりする。
世田谷編 2004年Page11 2004年Page12につづく
