旅人とわんこの日々
世田谷編 2006年Page11
世田谷(砧公園)での犬との生活をつづった写真日記です。
18、退職と旅人の苦悩(2006年9月)
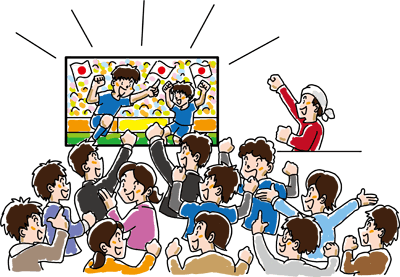
(*イラスト:hrukyさん 【イラストAC】)
今年は4年に一度の冬季オリンピック、そしてサッカーのワールドカップイヤーになる。サッカーワールドカップドイツ大会では、PK戦の末にイタリアがフランスを破り、24年ぶりに優勝した。
日本は、事前の期待は高かったものの、残念ながらグループステージで敗退。でも、前回の日韓ワールドカップの流れを引き継ぎ、盛り上がった大会となった。
ワールドカップやオリンピックのように数年に一度のイベント・・・と同じように扱ってはいけないのだが、色々あってまた仕事をやめることにした。
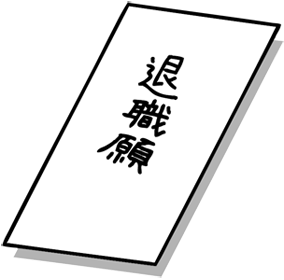
(*イラスト:阿部モノさん 【イラストAC】)
せめてオリンピックのように4年に一度ならもう少し盛り上がるのかもしれないが、私の場合はその半分の2年ぐらいでやめることが多い。
なので、周囲からの反応は、「またか・・・」といった感じ。いやいや、年数の問題ではない。いい歳なんだからちゃんとしろよ!といった半分呆れられた反応になる。
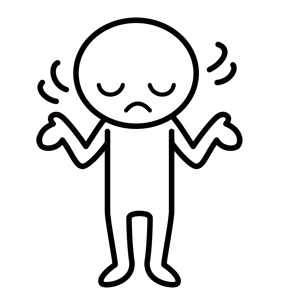
(*イラスト:ちょこぴよさん 【イラストAC】)
少し旅人の苦悩と言い訳を書いてみよう。誰しも職場に対して何かしらの不満を持っていることだろう。賃金や待遇、拘束時間、人間関係、労働内容、将来性・・・全く不満のない職場で働いている人は、ほんの一握りだと思う。
待遇、仕事内容などの悩みは、本人の努力や能力次第の部分があるので、給料が安いと思えば、自分が成長するなり、努力してもっといい職場を目指すしかない。特に私のように旅に出るために仕事を辞め、中途採用を繰り返している人間は、目をつぶらなければならない部分は多い。
どうにもならないのは、人間関係の方になる。ハラスメントをするような人は論外だが、普通に働いていても価値観の違いから人間関係がギクシャクし、深く悩むこともある。
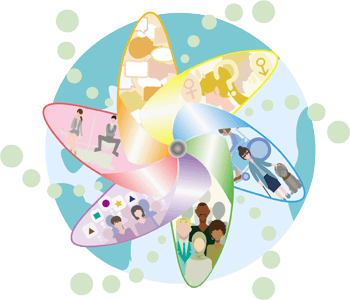
(*イラスト:syocoranさん 【イラストAC】)
人それぞれ、背負っているもの、目指しているものが違うので、働くことの意義とか、価値観、取り組み方が違うのは当たり前。
生きていくうえでの仕事の重要度も、生活に占める仕事の割合も、仕事への距離感や関係性も違ってくる。もちろん年齢や家族構成に拠る部分も大きく、独身か既婚、子育てや介護を担っている時と、そうでない時でも違ってくる。
私の場合、旅についてを第一に考え、そこから色々なことが派生していく。普通の人は軸が家族か、仕事となるのに対して、軸が旅、いわゆる趣味になっているから、他の人と価値観や行動、考え方にズレが生じてしまうことが多い。

(*イラスト:JamPanさん 【イラストAC】)
いくら私が並々ならぬ覚悟で旅に取り組んでいるといっても、他の人からしてみれば、旅は趣味や娯楽でしかない。こっちは生活が一杯一杯なのに、生活や言動が旅のことばかりで、人生に真剣味が足りないとか、考えや行動が軽いとか、いい加減とか、まあ要は輪を乱す存在のように思えてしまうようだ。
もちろんいい加減に仕事をしているつもりはない。それは胸を張って言える。でも他の人と同じことをやっていてもいい加減に見えてしまったり、好きなことをやっているので、嫉妬や反感を買いやすいのだ。
生き方や仕事に対する認識、社会的な常識がプラスマイナスを含めて一般的な感覚とズレているので、普通に働けばこうなってしまうのも当然といえば当然かもしれない。

(*イラスト:カフェラテさん 【イラストAC】)
もっと言うなら色々な土地を旅し、多くの文化を知っているし、転職の回数も多いので、これ違うんじゃない。こうした方がいいんじゃない・・・といった人よりも見えてしまうことも多い。
他の人よりも入社して日が浅いのに出しゃばると、お前に言われたくないとか、面倒くさいやつと煙たがられる。それはよくわかっている。なので、郷に入っては郷に従えとあるように、そのコミュニティーの中で可もなく不可もなく大人しくしているのが一番。私もなるべく最初はそうしている。
でも、好奇心旺盛なのが旅人。「こうやってみたらどうだろう。売り上げが上がらないだろうか。効率がよくないだろうか。」と頭に思い浮かぶと、どうにも試したくなってしまうのだ。
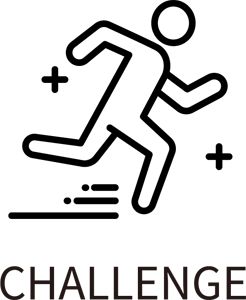
(*イラスト:人外さん 【イラストAC】)
疑問のままでは前に進めない。やっぱり何事もやってみないとわからないし、失敗から学ぶものも多い。というより、私の場合は一度失敗しないと理解が進まない。
で、積極的に行動をすると、余計な仕事が増えたり、失敗すれば、何やっているんだとなる。仕事を真面目に取り組めば取り組むほど浮いた存在になってしまうといったジレンマに陥り、このままここで仕事を続けていく意欲がなくなってしまった。

(*イラスト:ちゃむまっぴーさん 【イラストAC】)
入社の時は、「君の人と違った経験で、職場に新しい風を吹かせてくれ」と部長に言われたが、残念ながらここでは新しい風を吹かすことはできなかった。まあ今回は職場が自分に合っていなかったと思うしかない。

仕事を辞めてどうするんだ。今までと違って今回はちょっと深刻だ。若いうちは様々な経験をすれば、それは自分の血肉になっていくものだが、もうそういった歳ではなくなりつつある。
どちらかというと、地に足を付け、家族を持ったり、進む道を決め、責任感を持ってしっかりと生きていく年齢だ。それに求人の年齢制限にも引っかかるようになってきた。
こんな空中に漂うようなフワフワした生き方をしている場合ではないよな・・・。周りの人とどんどん差が付く一方だし・・・。そもそも将来が不安だ。
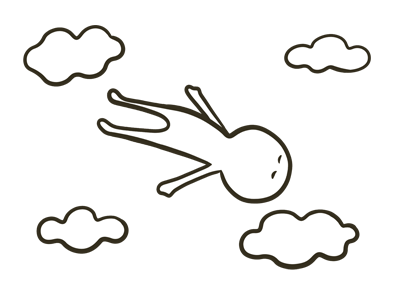
(*イラスト:ちゃむまっぴーさん 【イラストAC】)
自分の進むべき道というか、人生でやりたいことは分かっている。旅がしたい。でも旅を中心にすると、仕事がうまくいかない。旅というのは日常からの脱出。いわゆる脱日常が趣旨になる。旅に軸足を載せると、日常生活も地に足が付かなくなり、日常の中で浮いた存在となってしまう。
17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトの言葉に、「あまりに旅に時間を費やす者は、最後には己の国でよそ者となる」とあるが、日常での疎外感はまさにその通り。身に沁みて感じる。
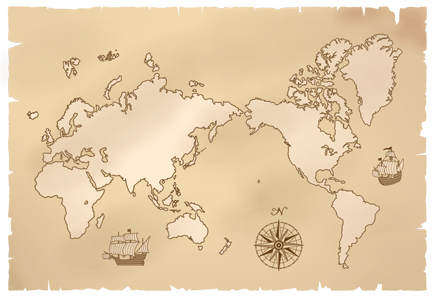
(*イラスト:まっきーばっはさん 【イラストAC】)
いっその事、何か旅で生計を立てることはできないだろうか。行きつくところはそこになる。それはずっと考えているのだが、旅は誰でもお金を払えばできてしまうことなので、生活できるだけの金を生み出すことは一筋縄ではいかない。
大航海時代なら、スポンサーを付けて黄金の国ジパングを見つけに行くといったこともできたかもしれないが、現代では飛行機に乗れば苦労せずにどこでも行けてしまう。
多くの場所を旅したので、私が訪れたお勧めの場所を紹介していくというのはどうだろう。これも希望薄だ。少し前まではそれも通用したのだが、インターネットが爆発的に普及したことで、珍しい場所というのも巷に溢れかえっていて、よほど珍しい場所を訪れない限り、凄いとはならない。
旅に限ったことではないが、クリエイティブなことをしようと思うなら、少なくとも人とは違ったことをするなり、何か新しいこととか、価値のあることを生み出さなければ、見向きもされない。
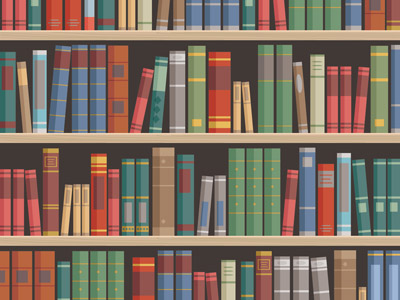
(*イラスト:白いねこねこさん 【イラストAC】)
かつては「旅は真の知識の大きな泉である<ディスレーリ>」「世界は一冊の本にして、旅せざる人々は本を一頁しか読まざるなり<アウグスティヌス>」「長生きするものは多くを知る。旅をしたものはそれ以上を知る<アラブの諺>」と言われたが、インターネットが普及した現代の情報化社会では、現実味のない言葉になりつつあるように感じる。
そう考えると、こんな誰でも簡単に移動でき、情報が溢れた便利な時代に旅をして生計を立てるのは至難の業というもの。なんていうか、車の運転がちょっとうまいからと、F1レーサーを目指すようなものではないのか。それはとんでもなく細く、想像を絶するような困難な道のりってことになる。
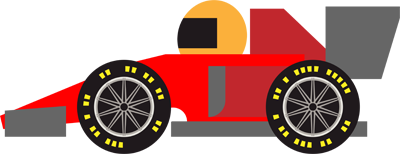
(*イラスト:スクラッチングマシーンさん 【イラストAC】)
というより、今からそんな世界を目指して大丈夫なのか。今までもインターネットで旅のホームページを公開しているが、鳴かず飛ばずの状態。困難を通り越して、無謀というものだろう。
そういったことを考えていたところに、職場の人と険悪な感じとなってしまった。我慢することを頑張れば解決するかもしれないが、それは余計に自分が苦しくなるだけ。これもいい機会だ。覚悟を決めて旅に取り組むか・・・と、今の職場を去ることにした。

(*イラスト:ちょこぴよさん 【イラストAC】)
歩く道のりが困難であるほど燃えるのが旅人というもの。困難な移動の過程を楽しむのが旅というもの。道が無ければ道をつくるまで。しっかりとした目標と、成功する確信、そして自分自身に自信を持って歩けば、必ず後ろに道ができる。
困難な人生かもしれないが、楽しみながら生きて行こうではないか。まあ今日まで何とかなってきたんだ。きっとこれからも何とかなるだろう・・・。
って、心の底からそんな楽観的には考えてはいない。もし、この夏に引退した中田選手のように実績も知名度も財産もあれば、どうにでもなるだろうが、全く何もない私では乗り越える壁が大きすぎる・・・。先行きが不透明過ぎて、将来が不安でしょうがない。
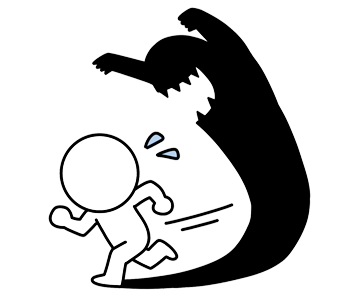
(*イラスト:poosanさん 【イラストAC】)
きっと今はよくても、最後には自分に跳ね返り、苦しい思いをするんだろうな・・・。有名なアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイの「あちこち旅をしてまわっても、自分から逃げることはできない」という言葉が、今、胸に深く突き刺さっている。
世田谷編 2006年Page11 2006年Page12につづく
