旅人とわんこの日々
世田谷編 2005年Page12
世田谷(砧公園)での犬との生活をつづった写真日記です。
16、モータースポーツの憂鬱(2005年9月7日)
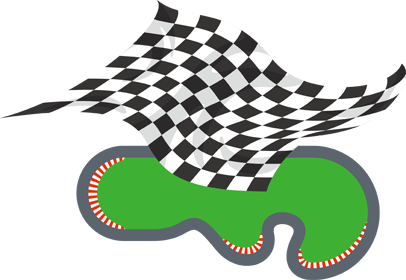
(*イラスト:K-factoryさん 【イラストAC】)
この前の日曜日は、今年参戦しているSLy チャレンジバイクレース第4戦の開催日だった。
この第4戦は1時間耐久レース。一人あたり30分しか走れないので、サーキットへ行く手間暇を考えると、参加することに旨味の少ないレースとなる。
ライダーの後輩Kは引き続き家庭の事情で不参加。えっ、また不参加。我が家のように親が病気をしているとか・・・。もしそうなら他人事ではない。心配になって何度か尋ねると、ようやく重い口を開くのだが、実は結婚式を控えているので、その準備や打合せで忙しい。とのこと。
なんだ。めでたい話ではないか。よかった。隠さず話してくれればよかったのに・・・と言うと、先輩が二人とも独身ということもあって、なかなか言い出せなかったとのこと。・・・。やれやれ、本当に困った先輩たちだ。って、しっかりしなくてはな・・・。
結婚という人生の一大イベントを前に趣味のレースに現(うつつ)を抜かしていたら、「結婚式よりもレースの方が大事なのね!」と、家庭を持つ前に家庭崩壊になりかねない。後輩が不参加の方がこっちとしても安心だ。
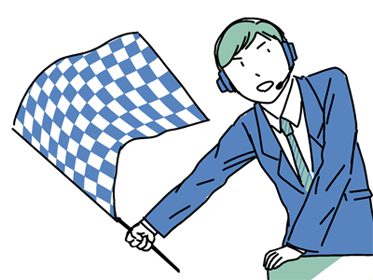
(*イラスト:てんうぃん☆さん 【イラストAC】)
後輩Kが不参加だし、レースも1時間だし、今回もまた不参加かな・・・。でも一応声をかけてみるか。友人が前回出場した後輩たちに声をかけてみるものの、1時間では触手が動かないようで、不参加の返事。サーキットがもっと気軽に行ける距離だったらいいのだが・・・。やっぱり山梨の韮崎はちょっと遠すぎる。
まあしょうがない。諦めよう。でも・・・、レースは練習走行とは違い、濃い密度で走ることができる。短時間とはいえ、レースでしか得られない醍醐味や経験は魅力だ。
友人はその狭間で迷いつつ、申し込み直前になって、「せっかくレースがあるし、場数をこなしておきたいし、最後、もう一回出走してくれない・・・」と、ライダー引退宣言をした私に声をかけてきた。
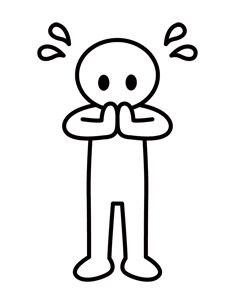
(*イラスト:ちょこぴよさん 【イラストAC】)
何が何でもレースに出ない。というわけではないので、友人の頼みならもう一度レースに出ること自体はやぶさかではないのだが、あいにくと父親の手術日がレース日の翌日なので、今回はちょっと厳しい。
全く練習をしていない状態で走れば、前回のようにコケてしまう可能性が高い。今度は打ち所が悪く入院。場合によっては、親子で同時手術ってことにもなりかねない。病人を抱え、崩壊しかかっている家庭が、それこそ崩壊してしまう。ってことで断り、今回も我々のチームは不参戦となった。
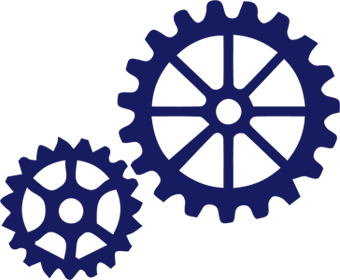
(*イラスト:hiraboさん 【イラストAC】)
冬の間、「今年は5戦全戦参加するぞ!」「表彰台に上がるぞ!」と張り切って友人たちとバイクを整備したのだが、もう既に2戦欠場。参加した2戦も、順位は最後尾付近。どうもうまく歯車がかみ合っていない。
というよりも、バイクレースの場合は、野球やサッカーみたいに「人が足りないから来てくれ。昼食をおごるから」というような感じで、簡単に助っ人を頼むということができない。後輩Kが今年結婚という時点で、楽観的過ぎる目標だったようだ。

我々が趣味で行っているレース活動は、世間ではモータースポーツと呼ばれている。スポーツと名が付いていると、さわやかとか、健康的といった健全なイメージを持ってしまうものだが、モータースポーツに限って言えばその限りではない。
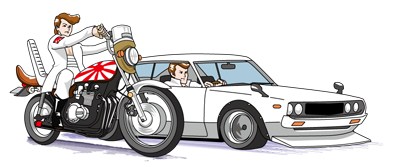
(*イラスト:kazukiさん 【イラストAC】)
どうも危険とか、不健康とか、エコじゃないとか、マイナスの印象の方が強い。暴走族とか、走り屋の延長上といった印象を受ける人も多いようで、一般受けも悪い。色々な面で一般的なスポーツとは一線を画しているように思う。
ちょうどいい後輩の例があるので紹介しよう。モータースポーツでは人間が扱えるギリギリのスピードで走行するので、怪我のリスクも高い。
バイクの場合だと、ライダーは頭部を守るヘルメット、革製のライダースーツやグローブ、脊髄を保護するための脊髄パッドなどの安全装備を装着して走行することになる。とはいえ、車のようにコックピットが囲まれていないので、転び方が悪いと大きな怪我をしてしまう。
よく見るようなコーナーでバイクが滑って、そのままお尻から路面を滑っていくような転び方だと、打ち身やねんざ、火傷ぐらいで済む事が多いのだが、バイクが跳ね上がって路面に叩き付けられるような派手な転倒になると、身体も路面にたたきつけられることになるので、骨折などの大きな怪我になりやすい。
それなりにスピードの出るサーキットとか、上位のカテゴリーでレースに参加していると、そういった大きな怪我をするリスクも必然的に高くなる。

(*イラスト:acworksさん 【イラストAC】)
後輩は、練習走行中にフロント(前輪)が滑って転倒。肩から地面に落ちてしまい、鎖骨をポキッと骨折。3日ほど入院することとなってしまった。そして、危うく会社を首になりかけていた。後輩のように色々と面倒なので、勤務先に知らせないでモータースポーツをやっている人も多いそうだ。
とはいえ、骨折程度の怪我ならサッカーにしても草野球にしても起こるのだが、一般的にサッカーや野球、或いはテニスなどといったものは健全なスポーツで、しょうがないとか、運が悪かったねといったことになり、モータースポーツの場合はそらみたことか、そんなことやっているから怪我するんだ。と、犯罪を犯したかのように印象が悪くなる。

(*イラスト:阿部モノさん 【イラストAC】)
後輩の話を聞くと、会社に黙ってやっていたのは悪かったけど、一生懸命やっていることに対して、上の人から不良とか、走り屋の遊びとしか思っていないような言い方をされ、そのまま会社を辞めようかと思うぐらい腹が立ったんだとか。
一昔前の話になるが、昭和の終わり頃、峠に行けば走り屋が命を削りながら競うように走り、町中では暴走族が爆音を立てながら騒々しく走り、社会問題になっていた。それを知ってる上司の世代にとっては、バイクは悪であり、レースもそういった走り屋や暴走族の延長としか思えない人も多い。
それなりのお金や手間暇かけて真面目にやっているのに、印象が悪いというだけで目の敵にされたり、単なる遊びと言われれば腹が立つのも当然だ。そもそも休日の過ごし方にまで口を出して欲しくない。


とはいえ、現実問題として、モータースポーツは取り返しの付かない大きな怪我をするリスクが高いというのも確かである。
実際、今回事故をしてしまい、入院するほどの怪我を負っている。更には、有給扱いにしてもらったとはいえ、急に3日休み、その後も骨が付くまで片手が不自由な状態で仕事をしなければならなく、随分と会社や同僚に迷惑をかけてしまっている。雇い主としても、社員にして欲しくない余暇の過ごし方になるだろう。
独身だとまだいいが、家庭を持つと状況は複雑になる。レースは一カ月に一回しかなくても、休日は練習か、マシンの整備をしなければならないし、ローンを組んでマシンなどを購入していることが多いので、ボーナスもほぼ消えていく。時間的にも金銭的にも大きな犠牲を伴う。
その上、大きな怪我のリスクもあるとなれば、最も家族に反対される趣味の一つであるのは間違いない。結婚を控えた後輩Kがなかなかレースに参加できないのも分かるし、結婚した後も今まで通りとはならないはずだ。

(*イラスト:ニッキーさん 【イラストAC】)
よくある話だが、レースをしている姿がカッコいいとか、素敵だと付き合い始め、理解のある配偶者と出会うことができたと、そのまま結婚することがある。
最初のうちは、夫婦で一緒にサーキットを訪れ、楽しくレースやその手伝いをすることだろう。友人などに、「うちの亭主は休日にバイクのレースをやっているのよ。この前は3位だったのよ。」と自慢話に花が咲くこともあるだろう。
でも、休日もサーキットばかりの生活に飽きてきたり、子供ができ、お金の問題が生じたりすると、不満が溜まっていくことになる。
そういった時に転倒して骨折などしてしまうと、更に家計が厳しくなり、「あなた、そんなにレースが大事なの?趣味なのでしょ。もういい歳なんだから、家庭も大事してよ。」と詰問され、選択を間違えると、家庭崩壊に・・・。やっぱりお金や時間に最低限のゆとりがないと、うまくいくわけがない。
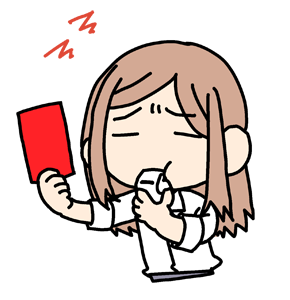
(*イラスト:羊毛種さん 【イラストAC】)
まあ普通の人にとってはモータースポーツは見るものであって、実際に自分でやろうとはならないものだ。命がけだし、お金は湯水のごとく消えていく。
興味のない人には罰ゲームをしているかのように思えるかもしれないが、かけるお金や手間暇、情熱が桁違いなので、とてもやりがいのある趣味であることは確かだと思う。ただ・・・、家族を含めた周りの理解が得られにくいのが難点ではある。
ちなみにモータースポーツは若い人が中心といったイメージがあるかもしれないが、実際はそうでもない。
全日本選手権や世界選手権に出場するような才能ある人達には若い人が多いが、お金がかかるので学生が気軽にとはならないし、安全性に問題があるので、親が積極的にやらせようともしない。
で、社会人になってある程度金銭的なゆとりができてから行う人が多く、走行会でも、レースでも30歳前後、それなりに歳をとっている人が多かったりする。

(*イラスト:ふじ丸さん 【イラストAC】)
最後に、レースとは関係ないが、大学時代にバイクサークルに入っていたからこそ感じるバイク乗りの憂鬱を付け加えておこう。
それは家庭内でのバイク乗りの肩身の狭さ。大学を卒業し、何年か経つと、ぼつぼつと仲間が結婚していくことになる。結婚した後も今までと変わらずバイクに乗って・・・という人はほとんどいない。当然というか、バイクを乗る機会が激減する。
子供が生まれると、さらに状況は悪くなる。「バイクは危険。もし事故に遭ったらどうするの。」「バイクに乗ってばかりいないで子供の面倒を見て。」と嫁に言われると、返す言葉がない。
細々と乗っていたのも罪悪感や周りのプレッシャーから乗れなくなり、子供が生まれたのをきっかけに、乗る機会がないからとバイクを売却する人も多い。

(*イラスト:gontyanさん 【イラストAC】)
そういった家庭にバイクに乗って遊びに行くと、とばっちりのように、「うちの旦那を誘わないでよ・・・」「うちの旦那がバイクを欲しがるからバイクで来ないでよ・・・」といった、奥さんから冷ややかな視線を浴びることもある。
バイクって世間で嫌われているのは常々感じているけど、家庭でも同じなんだな・・・と実感する場面であり、また、小さな子供がいるうちは色々なプレッシャーがかかり、本当に乗りにくい乗り物なんだな・・・と、仲間の気苦労と葛藤を感じる。
世田谷編 2005年Page12 2005年Page13につづく
